
【年齢別】こどもの歯ぎしりの原因と対策
こんにちは。
大阪市福島区の歯医者、かきうち歯科矯正歯科です。

「寝ているときに子どもが歯ぎしりをしている…」
そう感じたことはありませんか?
当院でもよく
”子どもが歯ぎしりしているんだけど大丈夫でしょうか?”
とご質問を受けます。
子どもの歯ぎしりは決して珍しいことではなく、成長発達の一環として見られることもあります。
しかし、年齢や状態によっては注意が必要です。
今回の記事では、年齢別に原因と対策を解説します。
年齢別の原因と対策

■ 0〜2歳:乳歯萌出に伴う生理的反応
主な原因 :乳歯の萌出期には、顎や歯の位置を無意識に確認するために
歯ぎしりが起こることがあります。
歯の生え始めた1歳未満の赤ちゃんでも歯ぎしりをすることがあります。
嚙むための筋肉や咬合刺激の発達に伴う自然な動きと考えられます。
対応策 :この時期の歯ぎしりは基本的に治療不要です。
ただし、頬や舌を噛むような癖が強い場合や、日中の異常な咬合行動が見られる場合は、
お口の中を傷つけないようにご相談ください。
■ 3〜5歳:乳歯列完成期・噛み合わせの調整
主な原因: 乳歯列が完成し、
自発的に噛み合わせを調整する目的で歯ぎしりをすることがあります。
また、環境の変化やストレス(保育園・幼稚園入園など)
も一因になることがあります。
対応策: 基本的に生理的な歯ぎしりとされ、経過観察でよい場合がほとんどです。
異常な摩耗や、日中の強い咬合癖がある場合は、咬合のチェックを行います。
必要によっては歯の摩耗分のレジン充填を行うことがあります。
また、異常な摩耗がある場合は心理的サポートが推奨されることがあります。
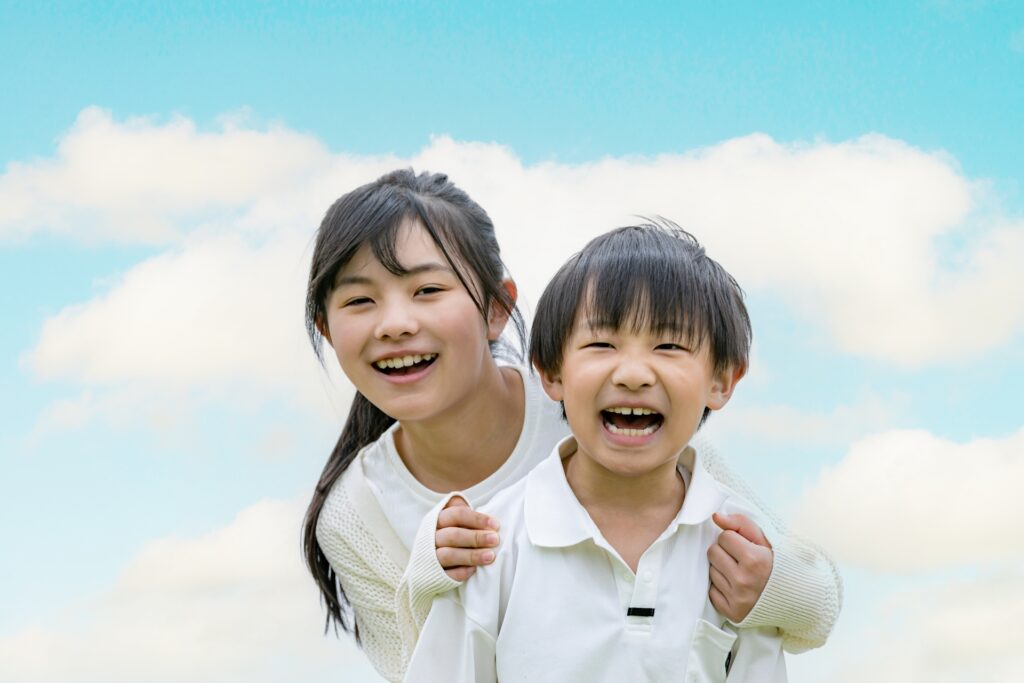
■ 6〜8歳:交換期初期の咬合変化と神経的要因
主な原因 :乳歯から永久歯への交換期にあたり、
咬合バランスが大きく変化する時期です。
特に前歯部の接触や咬合干渉があると歯ぎしりが出やすくなります。
また小学校入学により、集団行動など学校生活のストレスなどが誘因になります。
対応策 :歯の摩耗が強い場合は、咬合状態の診断を行います。
必要であればマウスピース(ナイトガード)の使用を検討します。
マウスピースは顎の成長にも影響するので十分な診査が必要となります。
歯の配列により、過剰な負担となっている歯がある場合などは
この時期から小児期の矯正治療を提案させていただきます。
また、睡眠環境や生活リズムの見直しも重要です。
■ 9〜12歳:咬合の確立と筋機能の過緊張
主な原因: 永久歯列への移行が進むこの時期は、上下の咬合関係の変化や、
習い事・学業などによる精神的負荷から、筋緊張性の歯ぎしりが生じることがあります。
対応策: 歯科的には、咬合干渉の除去、必要に応じてナイトガード装着を行います。
引き続きかみ合わせの負担が歯ぎしりを引き起こしていると
考えられる場合は、矯正治療の提案を行うことがあります。
精神的ストレスへの配慮として、保護者との面談や生活指導も有効な場合があります。

■ 13〜16歳:ストレス性・習慣性ブラキシズム
主な原因 :受験や人間関係などの精神的要因が主因になることが多く、
顎関節症状や頭痛を伴う場合もあります。
歯ぎしりが慢性化・習慣化することも。
対応策: 症状が強い場合は
・ナイトガードの使用
・咬合調整
・筋弛緩療法(開口訓練やマッサージ)
を組み合わせます。
心理的サポートが必要なケースもあるため、必要に応じて専門機関との連携も検討します。
まとめ
子どもの歯ぎしりは多くの場合、成長に伴う一時的な生理現象であることが多いですが、
年齢や症状によっては咬合や心身のトラブルが背景にあることも。
保護者の方々が
「様子を見ていい歯ぎしり」と「歯科受診が必要な歯ぎしり」
を見極めるのは難しいため、少しでも気になる症状があれば
いつでも当院までご相談ください。
院長 垣内 優一
経歴
- 大阪市福島区出身
- 日本矯正歯科学会 認定医
- 日本口腔インプラント学会 専修医

